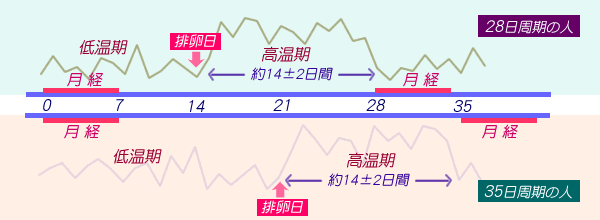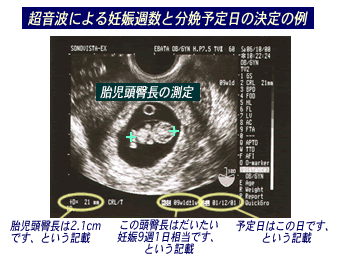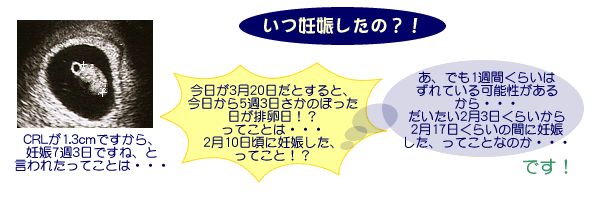生理が遅れているので市販の検査薬で検査してみたら陽性になった・・・あるいは病院で診てもらったら妊娠だと言われた・・・ということがわかると、
・いったい、いつできたんだろう
・今、妊娠何週(何ヶ月)くらいなんだろう
・予定日はいつなんだろう
ということが気になりますね。これらはすべて妊娠週数のお話しに関係あることなので、ここでまとめてお話しをすることにします。
○妊娠週数の定義
では最初に、どういう経緯で妊娠週数というものを定めるようになったのかについて、お話ししましょう。
昔から妊娠は十月十日(とつきとおか)といわれてきたように、おおよそ10ヶ月が妊娠期間であると考えられてきていました。そこで、正常に妊娠して出産に至った妊婦さんの統計を取ってみると、実際には妊娠期間(最後に生理があった日から分娩に至った日まで)はだいたい280±15日であることが判明しました。
このことを元に、WHO(世界保健機構)によって
・正常妊娠持続日数は280日とする
・28日を妊娠歴の1ヶ月と定め、妊娠持続を10ヶ月とする
・7日を一週と定め、妊娠持続を40週とする
・妊娠満週数で数えることとする
と定められたのが妊娠週数です。(下のイラストを参照して下さい)
この定義に従うと、最終月経開始日は妊娠0週0日となり、妊娠2週の開始日(妊娠2週0日)が14日目、妊娠4週の開始日(妊娠4週0日)が28日目で、この日(妊娠4週0日)から妊娠2ヶ月に入る、ということになります。
なお、この数え方でいくと280日目が妊娠40週0日(妊娠40週の開始日)となり、この日が分娩予定日となります。
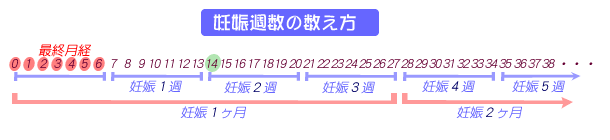
これは、順調に生理がある人の月経周期(生理が始まってから次の生理が始まるまでの期間)が通常28日間であることを考えると、妊娠期間はそのちょうど10周期分に相当するものであり、理にかなっているように思われます。
ところが、ここにはひとつ大きな問題点があります。
それは排卵日がいつなのか(=いつ赤ちゃんができたのか)ということが定義されていないということです。
WHOによる妊娠週数の数え方はあくまで「最終月経が始まった日から」数えるものであって、排卵日から数えるものではないのです。しかし、実際に赤ちゃんが発育し始めるのは排卵があり受精が起こってからとなりますから、排卵が大幅に遅れる可能性があった場合(生理が不順な人など)では同じように妊娠週数を数えていくと胎児の発育に遅れが見られるということになってしまいます。
では先述のWHOが定めた妊娠週数の中で、排卵日はいったいいつになるのか?、赤ちゃんはいつできたことになっているのか?、ということですが・・・
それは、28日周期で月経があった人の場合を当てはめて考えてみれば良いわけで、それからすると月経開始日から14日後、すなわち妊娠2週0日に相当する日が排卵日に当たる(上のイラストで緑色の○印がついているところ)ということがわかります。このことは、後でお話しする月経周期が不順であった人の場合の妊娠週数を計算する上で大変重要な意味を持つこととなります。以上が、妊娠週数の計算の仕方の基本となります。
○妊娠週数の数え方
生理の周期が一定している人の場合
月経周期が28日周期(生理が始まった日から次の生理が始まる日までの期間が28日間)である人は、先述のWHOが提唱した通りに数えれば良いわけですから、最終月経開始日を0週0日として数えていけばその日の妊娠週数がわかることになります。
では、例えば月経周期が35日周期だった人の場合はどうでしょう?
一般的に、高温期間はほぼ一定していておおよそ14±2日間であると考えられていますから、月経周期が35日周期であった人は、月経周期が28日周期であった人と比べると排卵日が約1週間遅れているものと考えられます。
下のイラストを参考にしてください。
よって、35日周期の人が妊娠した場合、28日周期の人に比べて約1週間遅れて妊娠しているものと考えられますから、その分胎児の発育も1週間ほどずれ込むことになります。ということは、35日周期の人は28日周期の人と同じ妊娠週数の数え方をすると、常に胎児が1週間ほど遅れて育っているということになってしまうわけですね。
したがって、35日周期の人の場合では排卵の遅れを考慮して、妊娠週数を約1週間遅らせる必要があるわけです。
同様に、40日周期の人なら12日間、45日周期の人なら17日間の調節が必要となる(=妊娠週数を遅らせる)ことになります。
生理の周期が一定していない人の場合
では、生理の周期がバラバラだった人の場合はどうでしょう?
この場合、いったいいつ頃に排卵があったのか(=妊娠したのか)が推測しにくいですね?
基礎体温表をつけていたのなら、それでも排卵日がいつだったのかをある程度推測することができますから、この場合は「排卵日が妊娠2週0日に相当する」ことを踏まえて妊娠週数を算出することができます。これについては、例を挙げて説明してみましょう。
下のような体温表を記録していた人がいたとして、5月9日に妊娠が判明したものとします。
さて、この人は5月9日には妊娠何週何日目になるでしょうか?
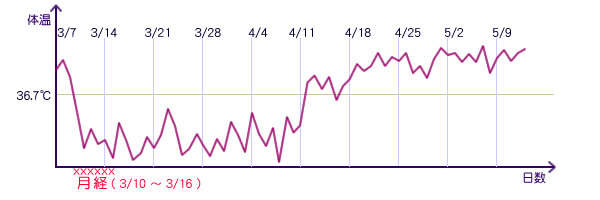
体温表を見ると、低温期から高温期へ移行したのは4月11日以降であると考えられますね。
したがって、排卵日をこの日と考えてこの日が2週0日に当たるものと考えれば良いことになりますから、この計算で行くと5月9日は4月11日のちょうど4週間と0日後になりますので、5月9日の妊娠週数は妊娠6週0日目になる、ということになります。
おわかりでしょうか?
もしも最終月経から妊娠週数を計算したとすると(つまり、最終月経開始日の3月10日を0週0日として計算すると)、この場合5月9日は妊娠8週4日目ということになってしまいますから、この数え方からすれば5月9日の時点では「胎児の発育が遅れている」と判断されることになってしまうわけです。
妊娠初期に「妊娠週数に比べて赤ちゃんが小さい」と言われて心配する方が多くいらっしゃるものと思いますが、実はその大半はこういうことなのだと考えて良いものなのです。さて、一方、基礎体温表も記録していなかった場合はどうしたら良いでしょうか?
この場合には排卵日さえ特定できないことになりますね?
このようなケースでは、胎児の発育具合を見て妊娠週数を決定するほかありませんので、超音波検査によって胎児の計測をして妊娠週数を推測することになります。通常、妊娠2〜3ヶ月(4週から11週)では胎児頭臀長(CRL ; crown-rump length)、それ以降では胎児大横経(BPD ; Biparietal diameter)の計測によって妊娠週数を算出するのが普通です。
○予定日の算出の仕方
妊娠週数がはっきりしたら、次は予定日はいつかということになります。
最初にお話ししたように、予定日は妊娠40週0日目になりますから、現在の妊娠週数から40週0日目になる日を計算すればよいわけですが・・・簡単な予定日計算機なり道具なりがあれば楽に計算もできますが、一日ずつ数えていくとなるとこれはかなり面倒なことですね。
そこで、簡易計算法(ネーゲレ法)が登場します。
ネーゲレは、以下のように最終月経開始日から簡単に予定日を算出する方法を提示しています。
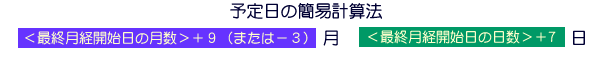
つまり、最終月経開始日が3月10日だとすると、予定日は3+9=12月、10+7=17日、すなわち12月17日だということになります。この方法で算出した場合、1、2日のずれが生じることはありますが、一日ずつ数えていって算出した予定日とほぼ合致するため、好んで用いられるものですが・・・
やはり問題点は「最終月経開始日から」算出という点ですね?
よってこれを排卵日から算出するようにすればもっと確実になることになりますので、排卵日が2週0日に相当することを利用して計算式を考えてみると、
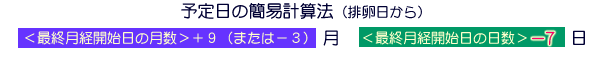
で良いことがわかります。
最近では、簡単に予定日を計算することができる計算機が普及していますので、こうして簡易計算法で予定日を算出することは少なくなりましたが、機械が壊れていていちいち計算するのが面倒くさい(笑)ような時には非常に便利な計算法なのです。
ただし、この計算法は「最終月経の開始日」から計算する方法ですので、 何度もお話してきたように28日周期で生理が来ていた人にとってはほぼ正確な予定日であると考えて良いものですが、生理が不順であったり生理の周期がかなり長かったりした人の場合には、この計算法によって算出された予定日とはかなりズレが生じるものと考えた方が良いことをお忘れないように。
○いったい、いつ妊娠したのか?
さて、以上のような妊娠週数の数え方を知らなくても、病院では先生が診察して今妊娠何週何日で分娩予定日はいつであるということを教えてくれます。
で、妊娠だとわかった、予定日もいつだかわかった・・・
じゃあ、いったいいつ妊娠したの?ということですが。
今までお話ししてきたことを考えると、妊娠週数がはっきりした時点で、その週数から2週間分をひいた分だけさかのぼった日が排卵日に相当することがわかりますよね?例えば、いま現在妊娠7週4日ですよと言われたものだとすれば、それから2週間をひいた分、つまり5週間と4日さかのぼった日が排卵日・・・すなわち、その頃に妊娠してできたということがわかるというわけです。ただし、超音波による胎児計測から算出した妊娠週数には約1週間ほどずれが生じる可能性がありますから、これによっていつ頃妊娠したのかを推定する場合も前後1週間ほどずれている可能性は否定できないことを頭に置いておくようにしましょう。